「日本語を教わっていない」東大生
受験対話総合研究所の講座には、小学校、中学校時代の不登校を克服した大学生がたくさん来ています。
先日も、「国語は高校で習ってきたけれど、日本語はまだ教わってない。だから…」と言って、「ことば」の講座に参加してくれた東大生がいました。彼は、小学校5、6年生、中学校1、2年生時代に不登校だったと言いました。東大に入って、入社試験の面接を目前にして、初めて「日本語」を習ったことがなかったと気づいたそうです。
彼だけではありません。学校に通っていても、いなくても、自分の人生を決める「入社面接」という現実にぶつかって、若者たちは、はたと困惑するのです。
これまでは、人に何事か感想を聞かれても「はぁ、別に」とか、「まぁ、そんなところですか」とつぶやいていれば済んだ。 ところが、今度はそうはいかない。
そうはいかないばかりか、大切な人生を左右する「面接」では、未知の人と向き合って、ちゃんと話さなきゃならない。しかし、改めて考えてみると、「ちゃんと話す」とは、どうすることなのか。そこのところが、よくわからない。

「ちゃんと話せ」と、子どもの頃から、親や先生に言われ続けてきたものの、何が「ちゃんと」の中身なのかは、まるで教わっていない。「ちゃんと」の中身も教わらなかったし、その技術も教わっていない。「ちゃんと」話すためには、どうやって言葉を選ぶのか、どんな組み立てをつくればよいのか、「正しい日本語」とは、「美しい日本語」とは…。
「今の若者の言葉は…」という叱責の声は聞こえるけれど、具体的にどうすればよいのか。誰も教えていない。親も教師も。
学校に通っていても、いなくても、関係ない。
なんとかしなくてはならない。
「ちゃんと」とは何か。
「体験」こそが言葉
「ことば」は学問ではないし、知識でもない。人間そのものです。
この人間そのものとは、どういう意味なのか?
高校生、大学生を30年指導してきた「受験対話」の結論は、「体験だ」ということです。
「ことば」は、自分の歴史(体験)であると同時に、人と人の間を埋めるもの(体験)であり、自分と社会をつなぐもの(体験)です。
学校に通っていた大学生たちも、ここを教わってきていないのです。
不登校の学生だって、正解が用意されている入学試験の勉強は、やれば、短時間で出来ます。
この短時間で試験勉強を終えるためには、「土台づくり」が必要なのです。

「ことば」は自分と社会をつなぐ絆
不登校児と言われているキミ、「ことば」の勉強をしよう。
「ことば」は、自分と社会をつなぐ絆です。
論理を持ち、社会性が備わる。
人と交わった、その体験が「ことば」を育てていくのだし、人間関係をさらに築いていくことができるのです。
「ことば」と人間関係は、「あざなえる縄」のごとく、切り離せません。
だから、人間関係がつかめなかったり、見えなかったりすると、「ことば」も不分明にならざるをえないのです。「ちゃんとした言葉」を獲得するということは、「ちゃんとした人間関係」を築くということと表裏のものなのです。
目標は「対話」ができるようになる
この講座では、不登校の子どもたちが、社会の中で、その場にふさわしく、相手にふさわしく、自分にふさわしく「対話」ができるようにします。その能力を持つことが「ちゃんと」話すということなのです。社会の中で「ちゃんと」振る舞う姿勢こそが、自分の「ことば」を育てるのです。ここまでくれば、少し楽に生きられるようになります。次第に、不登校について、原因の究明や対策を考えられるようになります。
SNSが発達した現在、いろいろな専門家とつながることができるようになりました。学校を飛び越えた勉強の機会も、自分で作れるようになりました。学校に通っていなくても、興味のあることはあるはず、好きなことはあるはずです。自分の好きな人、興味のある人に会ってもらえるように、まず自分を磨くのです。「自分のことば」を磨くのです。
会いたいと思った人に手紙を書きます。会ってもらい、自分の「情熱」を伝えます。
そして仲間に入れてもらいます。
不登校だろうが何だろうが、「楽しく、充実した時間(人生)」を自分でつかみ取ろう!まずは、学校以外に、専門家と話ができる自分の居場所をつくる。これが、この勉強会の最初の目標です。
肩に力なんか入れるな。楽な気持ちでいい。
まずは、ちょっとだけ勉強を始めよう!オンラインで!
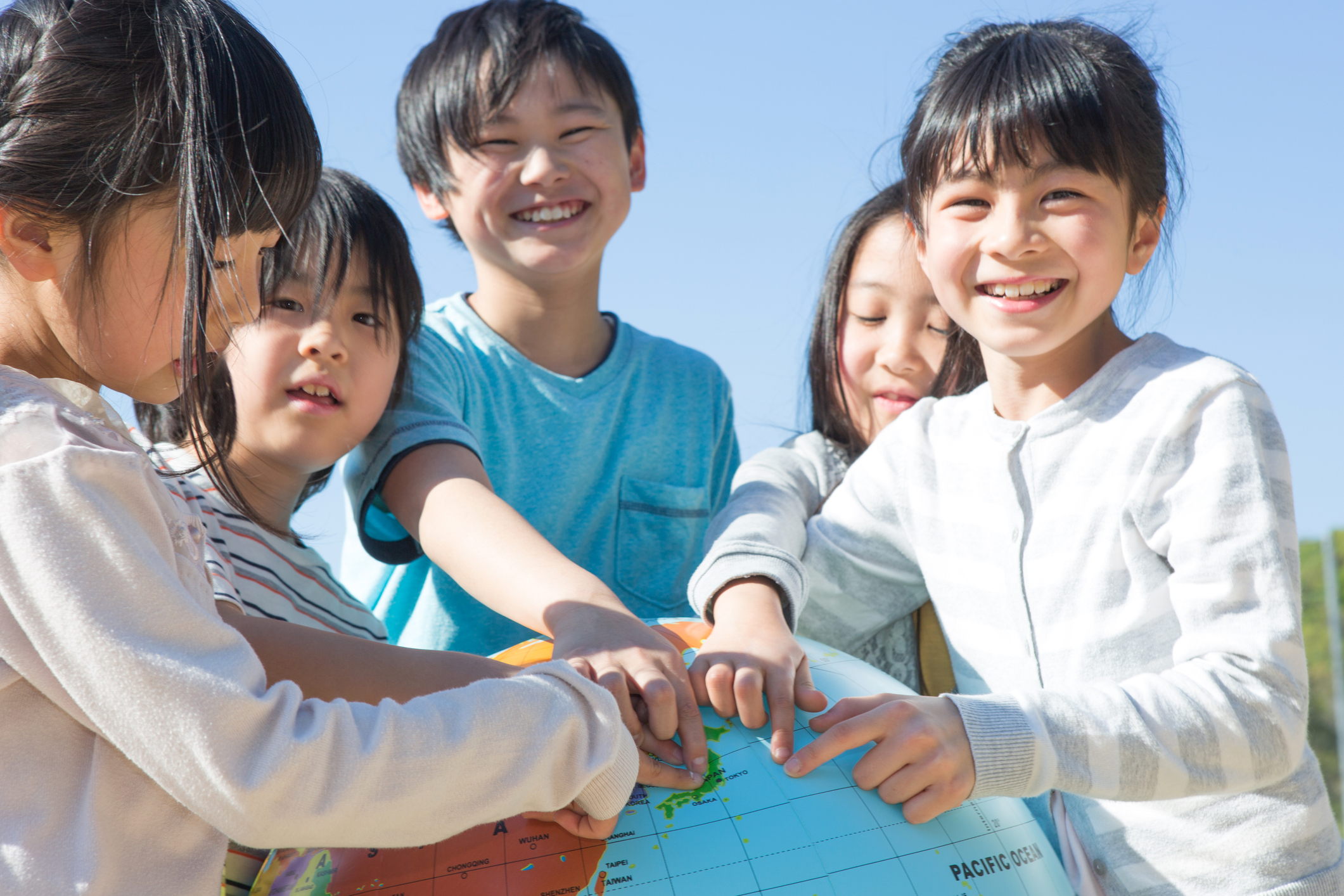
ギリシャの哲学者アリストテレスが「対話の神髄」を聞かれて、「最もたいせつなのは、アティチュードだ。そして2番目もアティチュードだし、3番目もアティチュードだ」と述べたと言われています。(デモステネスだという説もある)
これは、「ことば」の伝わるダイナミックスを、見事に言い当てているのではないかと思うのです。この際のアティチュードとは、日本語に訳すと、姿勢とか態度、心構えという意味をも含んだ言葉です。言語だけの問題ではありません。「ことば」を届けようとする、あるいは受け取ろうとする姿勢、態度、心構えが「対話の力」を決めるということです。
アメリカから来た大学生と日本の不登校の小・中学生の合同イベントを行ったことがあります。言語の障害を乗り越えて、一つのパズルを作り上げるのです。ときには筆談、ときには手まね足まね、絵を画いて理解し合ったこともしばしばありました。イベントが終わって、多くの学生たちが、強い友情で結ばれました。
参加したイェール大学の学生が言いました。
「言葉が通じないという、そのことが、かえってコミュニケーションを深めることに役立つなんて、思いがけない発見でした。自分の考えていることを、日本の子どもたちにわかってもらわないといけないし、小中学生が何を思っているのかわからなくては、パズルはできませんからね。言葉が通じない分だけ、一生懸命になるでしょう。だから、いっしょに障害物を乗り越えた連帯感が生まれたのです」
そう。アティチュードの問題だというのは、ここなのです。「ことば」を理解しようとする姿勢なのです。そして、人間関係への姿勢です。
このイベントに参加した子の多くが、「自分の道」を自分から歩き始めました。
「体験」すること、そして「わかってほしい」と真剣に自分の思いを相手に伝える努力をすること。
不登校で悩んでいる子どもたちに、この姿勢を身につけてもらいます。

自分の人生を楽しく充実したものにするために、
一人で歩けるようになるまで一緒に歩きます。



